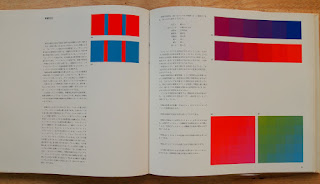クロッキーの場合はともかく、それなりの時間をかけてデッサンができる時は、最初にモデルさんを良く測って、頭・胴・腰・腕・足などの大きな位置関係を決めること大切です。その際、直線で垂直・水平を基準に取っていくことで画面に対する位置関係を探っていきます。
クロッキーの場合はともかく、それなりの時間をかけてデッサンができる時は、最初にモデルさんを良く測って、頭・胴・腰・腕・足などの大きな位置関係を決めること大切です。その際、直線で垂直・水平を基準に取っていくことで画面に対する位置関係を探っていきます。次に斜線による対象の傾きを引いていきます。
部分的に引くのではなく、延長した線が他の形態のどこに行くのかを見ることが狂いの少ないデッサンを描くコツです。
人体の具体的な形を描き始めたところです。
現実のモデルさんの輪郭を見ると曲線の連続に見えますが、それをそのまま描こうとすると形の甘いデッサンになりがちです。あえて直線で捉えることで、形の変化する位置や線の長短を意識して描くようにしています。
大きな形が決まってきたら、次第に直線の中に曲線(円弧)をはさむように加えていき、人体の柔らかさをだします。
明暗の境を決めて影をおいていきます。
白チョークで明部を描き起こし始めたところです。
目に最も近い所から白チョークを置いていき次第に周囲に広げていきます。
擦筆やセーム革を使って浮いたチョークを馴染ませ、滑らかなモデリングにします。
細部はチャコール鉛筆の白を使っています。
 |
| 裸婦デッサン (540×370) ミタント紙にチャコール鉛筆の白と黒、白チョーク |